こんにちは!
お金より、地位より、愛・・・より、褒められたい・・・ドクターコンちゃんです!
人を教育するときの有名な言葉に、
”やって見せ 言って聞かせて させてみて ほめてやらねば 人は動かじ”
というのがありますね。
第2次大戦で艦隊を率いた山本五十六の言葉だそうです。
オペの上達は職人の手仕事に似ているので、
この言葉の重みがよくわかります。
ただ、ボクが医者になったころは、
日本の医師世界は、
今と違ってまだパターナリズム(父権主義)が主流でした。
その当時の回顧録とともに、最近の風潮もお話してみます。
やって見せ・・・てもらってないし(´・ω・`)
研修医になりたての頃、
上級医の手術に助手として入るのですが、
そもそも、良くて第2助手で、だいたい第3助手以下であることが当たり前であり、
狭い術野に4人も医者が頭を突っ込んだら、第3助手なんかには、
もう何が行われているのか全く見えないのです。
そのくせ手術記録を書くのは下っ端の仕事なので、
教科書を参考にとりあえず想像で書いて上級医に持っていくと、
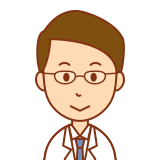
こんなことやってねーよ!
と言われる始末。
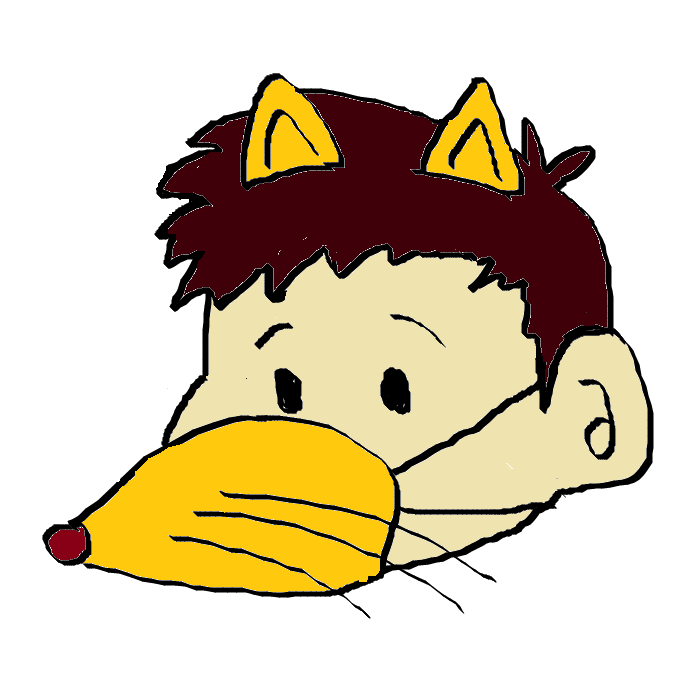
(見せてもらってねーし・・・!!!)
と、いつも心でぼやいておりました。
職人の世界では昔から、

いちいち質問すんじゃねえ!!!
見て覚えろ!!!
みたいなところがあると思いますが、
外科医の世界も似た感じでしたね。
もはや、昔どっかの偉い人が言っていた、
Don’t think, Feel.(考えるな、感じるのだ・・・)
みたいな。
昔いた、どっかの偉い人 ↓

それでも、難しいオペなどを、第2、第3助手として多少は見れることもあり、
後に自分がオペするようになった時に、
「ああ、あの時あの先生がこうやってたなあ」
と思い出して対応できることもあるので、
見て覚えるというのも、あながち間違いでもないかと。
でも、やっぱりその時に良く見て、
疑問をすぐ質問できた方が、理解と上達は早いですよね・・・。
言って聞かせて・・・もらってないし( ゚Д゚)
先ほどのように、
まず見れていないのでは質問のしようもないのですが、
当時、オペ中にたまに質問すると、
黙殺されることもありましたね( ;∀;)
今になって思うと、当時のボクの知識がショボすぎて、
あまりに初歩的なことを聞いてしまっていたかもしれません。
確かに、せめて教科書レベルのことは予習できていないとね、
と、オジサンになると思います。
でもボクは、自分が若い時の苦い経験もあるので、
自分が指導医の立場になったとき、
研修医の右も左も分からない子と、二人きりのオペになったときも、
「これが〇〇で、今何をしていて・・・」
と、極力説明するようにしていました。
ただ、昔の自分と重ね合わせて目の前の研修医を見た時、
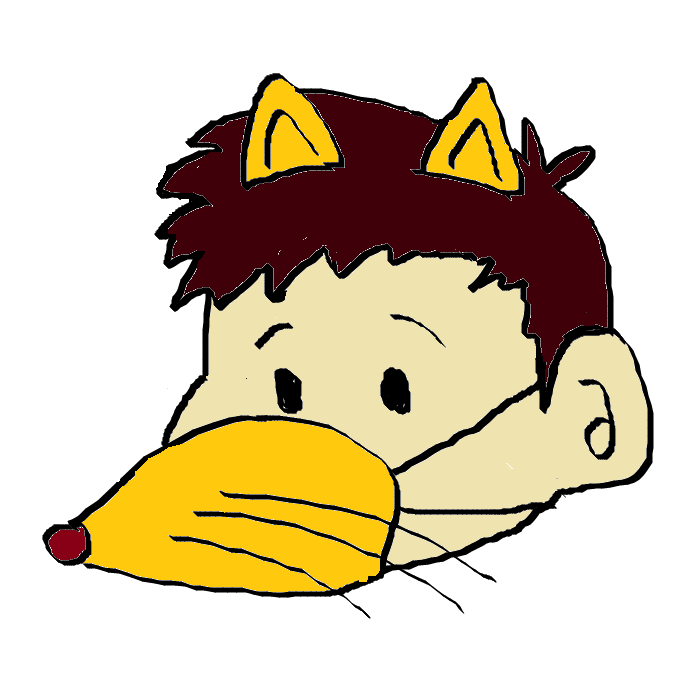
果たしてどれだけ伝わっているのだろうか・・・?
と不安にもなったものです。
させてみて・・・もらってないし(/ω\)
もちろん、若手には、なかなかさせてもらえません。
でも、今になって思えば、
若手に対して、自分のオペに手を出させるのは、
執刀医としてはコワイものです。
ただ、自分がオペするようになると、
やってみないと分からないコトがいっぱいあることに気づきます。
結局、
(先輩のオペを)見る → (質問して)聞いて教わる → やってみる → また疑問がわく → 見る → (見ても分からない点を)聞いて教わる → やってみる・・・
のループを回して上達するしかないワケです。
なんか、ビジネス界隈で言われる、
PDCAサイクルに似てますね。
Plan(計画) → Do(実行)→ Check(評価)→ Action(改善)
ってやつですね。
やってみなければ、いくら勉強してもオペできるようになりません。
ただし、オペについては失敗が許されないので、
指導医が、若手にどこまでやらせていいか判断して、
指導医の責任でやらせてみて、
あぶなければすぐストップをかける必要があります。
これは指導医にとって相当にストレスです。
やらせる間は時間もかかるので、
周りのスタッフのプレッシャーも感じますしね(^-^;
ただ、ボクは少しずつでも若手にやらせなきゃと思って、
皮膚の縫合とか、
自分がドキドキしないレベルで、研修医にやらせてみたりはしてました。
ほめてやらねば 人は動かじ・・・ほめられなくても頑張るもんねっ(>_<)
もちろん、ボクはほとんどほめられたこと無いっすよ!!(^^)!
でも、たまに少し年上の先生から、
根拠なく褒められた時、やはりうれしいものでした。
山本五十六的な考えに基づく、お世辞かなと思いましたが、
うれしいものは、うれしいと。
昔の職人の世界においては、
いちいち教育してもらえなくても、
上を目指して努力するっていうのは、
大変な自己肯定感とハングリー精神が必要ですよね。
時代背景もあるのでしょうが、今風でないことは明らかです。
しかし、自分の責任でやらせてみて、
ただでさえハラハラするのに、
(ヘタクソであっても)ほめなきゃスネちゃって、
動いてくれなくなっちゃうって・・・
もう、ホント、
わがままアイドルのマネージャーじゃないんだからって感じですが(;^ω^)

ほめてくれなきゃ、オコなんだからね!
もう、イベント出てやんない!
みたいなね。
そんなことボヤいていると、
ボクも前時代的な人間と思われるのでしょうね(^-^;
自分が育った環境を正当化しようとしてしまう、人間の性質でしょうけど、
気をつけねばと思います。
しかし、あらゆるところでパターナリズムが蔓延していた昭和時代に、
軍人がこういった考えをもっていたことはオドロキです。
『ハーバードの医師づくり』って本
そういえば、医学生の時に読んだ本で、ハーバードの医師づくりって本がありました。
アメリカの形成外科研修を受けた著者が、
ほとんど何もできない時に、
オペに一緒に入った上級医が、「やってみろ」と手を出させてくれて、

エクセレント!
と大げさに褒めてくれたとのエピソードがあったと思います。
アメリカでも昔はパターナリズムであったようですが、
徐々に、若手に優しい、
まさに山本五十六の言葉通りの教育方針に変わってきたそうです。
最近の若手医師教育
文化的にあらゆる面でアメリカの後追いをしている日本において、
最近、やっと医者世界の教育方針も、
アメリカに追いついてきたのかな、と思います。
ボクが若い時みたいにほったらかしではなく、
研修医に積極的に教育をするというスタンスが、
当たり前になりつつあると思います。
背景には、新研修医制度の発足により、
昔みたいにいきなり専門領域の大学医局に属するのではなく、
2年間、いろんな科を回って研修を積むというスタイルに変わったこともあると思います。
各病院が、若い働き手を確保するために、
教育にも力を入れてますよ!とアピールする必要があるからです。
ボクらの頃のように、
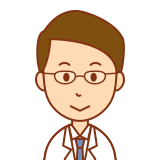
教えないし、やらせないし、当然褒めないけど、とにかく見て覚えろ!
みたいな病院には、やる気のある研修医は応募しませんからね(^-^;
当然、昔と違って、指導医の負担も増えているでしょうケド。
最近では、研修医の働き方も見直され、
パワハラ医師は訴えられ、
研修医の労働環境はうらやましいくらい改善しています。
ただ、医学教育に関して先進的なアメリカでも、
人気のある外科系の若手研修では、
ほとんど家に帰らなかった、昔のボクらの研修医時代のように、いまだに激務と聞きます。
競争を勝ち抜いて、良いポジションにつくためには、
若いうちは耐える必要があるという、
まさに競争社会アメリカといった感じでしょうか。
巷の噂で聞いた、
日本企業と、外資系企業の働き方の違いにも似ている気がします。
まあ、アメリカみたいに、耐え抜いた後のご褒美が約束されていなければ、
単なるブラック労働として、やる気がなくなってしまうので、
日本においては、ますますの医師の働き方改革に期待です。
まとめ
オジサンになっていくと、
教育って難しい、
まず自分が育つ必要があるとホント感じます。
教えることが学びになるとは使い古された言葉ですが、
そういう立場になって、考えてみなければ実感できないもんですね。
でも、いくつになっても、やっぱり自分も褒められたいですよねっ。
というワケで、
自分を褒めて褒めて褒めちぎって頑張りましょう!
最後まで読んでくださって、
ありがとうございました~!!!
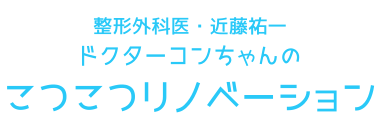




コメント
I agree with you.
I’m very interested in the book Harvard Medical School.
This reminds me of enhancing effects. Praise really motivates us to challenge🙌